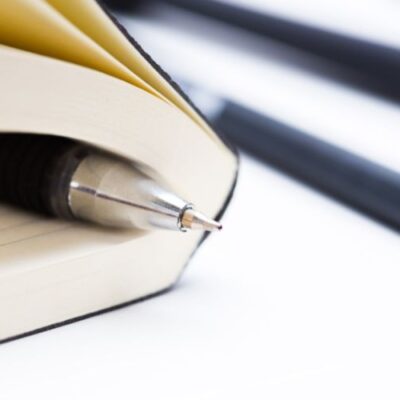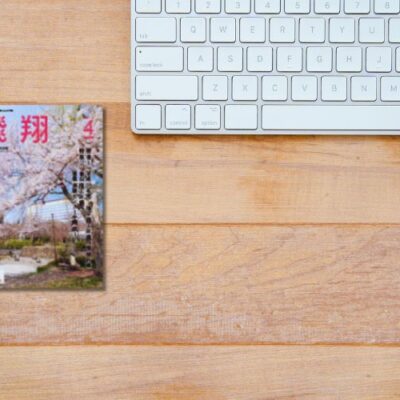がんばるの心理

「がんばります」と言うたびに、現場が止まっていないか
「がんばります」と口にする人は少なくありません。
報告の最後、上司からの期待に対して、あるいは自分を奮い立たせるように。
一見、前向きな言葉に聞こえますが、職場を見渡すと、「がんばります」と言いながら、行動が変わらない人が多いのも事実です。
なぜ、この言葉が出る人ほど、実際の変化につながらないのでしょうか。
1.「がんばります」と言うたびに、現場が止まっていないか
2.「がんばります」の裏側にある3つの心理
3.がんばる前に、段取りを考える
4.「がんばります」を行動言語に変える
5.「がんばり」を行動に変える力を育てる
「がんばります」と口にする人は少なくありません。
報告の最後、上司からの期待に対して、あるいは自分を奮い立たせるように。
一見、前向きな言葉に聞こえますが、職場を見渡すと、「がんばります」と言いながら、行動が変わらない人が多いのも事実です。
たとえば、毎月の営業会議で「今月も結果が出ませんでした。来月こそがんばります」と真摯に反省を述べる部下。
ところが翌月も同じ言葉が繰り返され、状況はほとんど変わっていない。
努力していないわけではなく、「がんばる」と言うことで安心してしまう構造がそこにはあります。
また、あるリーダー会議。
業務改善のテーマとして「報告ミスを減らそう」と決めたにもかかわらず、翌週も同じミスが発生する。
担当者は真剣な表情で「確認を徹底します」「次はがんばります」と繰り返す。
しかし、具体的にどの工程で確認するのか、誰がどうチェックするのかが決まらないまま時間だけが過ぎていく。
「がんばります」と言えば前向きに聞こえるが、実際には行動の設計が止まっている状態です。
「がんばります」の裏側にある3つの心理
「がんばります」という言葉には、3つの心理が隠れています。
1.「自己防衛的努力志向」です。
「がんばる」という言葉は、具体策や結果ではなく姿勢を示す表現です。
成果や方法が見えないとき、「とにかくがんばります」と言うことで、誠実さや努力を示し、評価を下げられないようにする心理が働いています。これは責任回避ではなく、「努力している姿勢で自分を守る」防衛的行動です。
2.「曖昧な自己効力感の表れ」です。
具体的な行動計画を描けない、あるいは自信が持てないとき、人は「がんばる」という抽象的な言葉で意欲を代替します。
「やる気」はあるのに「やり方」が見えない──その不安を覆い隠すために、言葉で気持ちを整えているのです。
3.「承認への渇望」です。
「がんばります」は、相手へのメッセージでもあります。
「私は真剣です」「期待に応えようとしています」と伝えることで、上司や仲間からの承認を得たいという心理が働きます。つまり、努力そのものを見てほしいという願望の表出です。
したがって、「がんばります」が口癖の人は、行動の不明確さよりも評価や信頼に対する不安が根底にあります。
がんばる前に、段取りを考える
ビジネスパーソンの多くは、「がんばる=良いこと」と信じています。
しかし、とくに組織を動かす立場にある管理者に求められるのは、がんばりではなく段取りです。
どれだけ努力しても、段取りを誤れば成果は上がりません。
がんばる前に、「何を、どの順番で、誰と進めるか」を考える。
この一手間があるかどうかで、仕事の質もスピードも変わります。
がむしゃらに動くより、先に道筋を描く。
それが、チームを確実に動かす管理者の「がんばり方」です。
「がんばります」を行動言語に変える
管理職が「がんばります」から抜け出すには、言葉を行動言語に変えることが第一歩です。
研修で成果を出す管理者ほど、言葉が具体です。
たとえば、
「がんばります」ではなく、
「朝礼で一人ずつの発言を増やすために、明日から問いを一つ投げかけます」
このように行動が見える表現に変わると、意識は一気に実践モードに切り替わります。
「がんばります」と言う管理者と、行動を明確にできる管理者の違いは、学びの抽象度と内省の深さにあります。
前者は学びを意欲レベルで止めています。理解や共感は得たが、それを自分の業務に置き換える作業が終わっていません。
一方、後者は学びを自己の現場文脈に再構成できています。
「何を」「どの場面で」「どのように」変えるかを具体化しており、思考が行動レベルまで落ちています。
この状態になると、「がんばる」という言葉は不要になります。なぜなら、やることが見えているからです。
「がんばり」を行動に変える力を育てる
「がんばる」は悪い言葉ではありません。
しかし、それを行動に翻訳できなければ、組織は動きません。
「がんばります」と言う人を責めるのではなく、彼らは「理解したつもり」から「実践に落とし込む」途中段階にいます。
支援の焦点は、「学びをどう現場の行動に翻訳するか」です。
たとえば、「どんな場面で、そのがんばりを発揮したいと思いましたか?」
と問いかけるだけで、意欲が行動設計に変わります。
あなたの「がんばります」は、誰に、どんな行動で伝わる言葉になっていますか。
もっと詳しく学習したい方へ
管理職が育てば、会社が伸びる「育成マネジメント」: 「任せる・育てる・信じる」あなたのチームが動き出す!
本書では、「任せる・育てる・信じる」という行動原則を通じて、管理職が“自律的に動く現場”をつくることを目的としています。
このとき重要なのが、「意欲(がんばり)」を「行動」に変える構造です。
今回のコラムはまさにその転換点を扱っています。
「がんばります」と言う管理者が、意欲レベルで止まり、行動設計に至っていない心理的段階にあることを可視化しています。
したがって本テーマは、書籍「第4章:信頼されるリーダーが実践している日常行動」と「第5章:「育成マネジメント」を仕組み化し、組織全体を動かす方法」の中にある「意欲を行動に変える支援」と同じ問題意識を考察することができます。
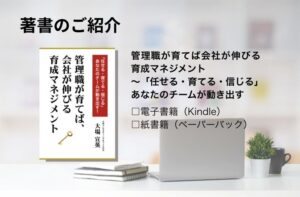
理念×行動=自律するチーム: 理念を行動に変える自律するチームの実践体系
本書では、「理念を“行動言語”に翻訳する」ことが中心テーマです。
つまり、“良いことを言う”段階から、“行動で示す”段階へどう移すか。
「がんばります」が形骸化した言葉になってしまう構造は、まさに理念が形だけで浸透しない現象と同じです。
どちらも「言葉が行動に変わらない」ことが根本課題です。
したがって今回のテーマは、理念の「唱和止まり」問題の縮図です。
理念が抽象語で止まるように、「がんばります」もまた行動に変わらない抽象語です。
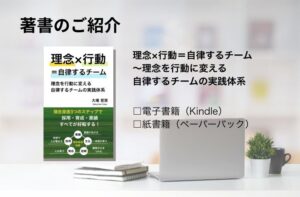
がんばるの心理