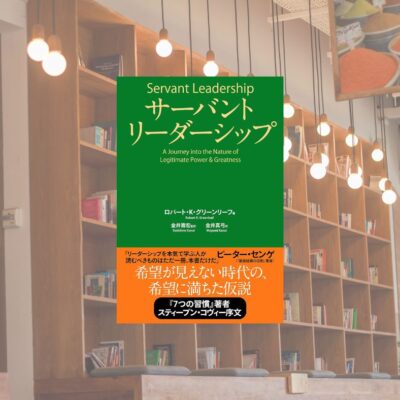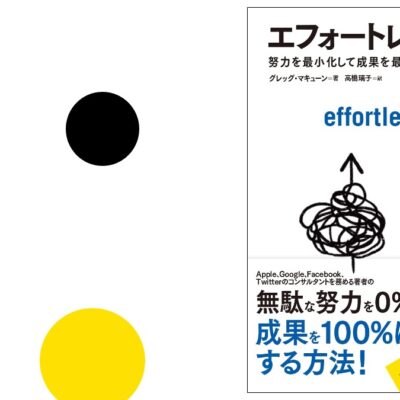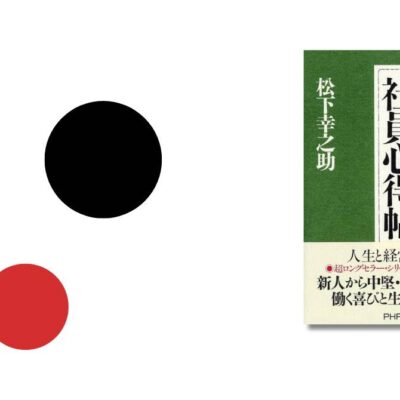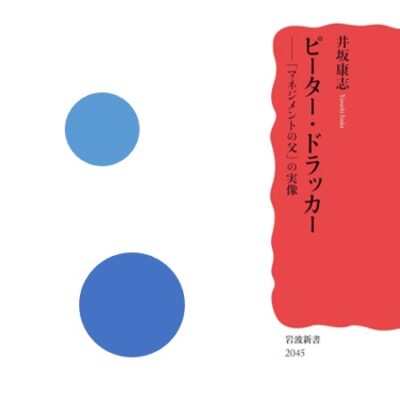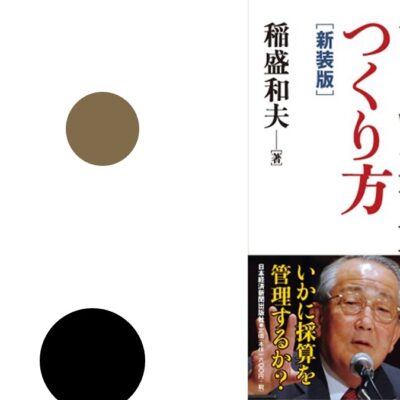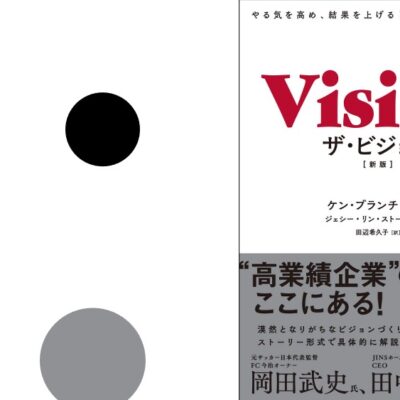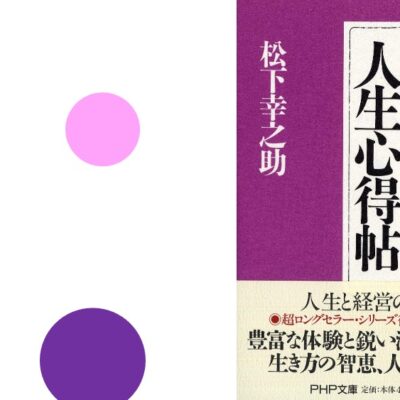ファクトフルネス:10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
「FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣」私の読書メモを紹介します。
著者:ハンス・ロスリング 他
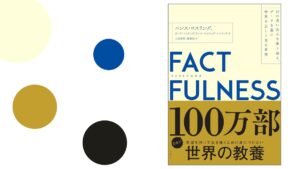
目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
ファクトフルネスとは、話の中の分断を示す言葉に気づくこと。それが重なり合わない2つのグループを連想させることに気づくこと。多くの場合、実際には分断ではなく、誰もいないと思われていた中間部分に大半の人がいる。分断本能を抑えるには、大半の人がどこにいるかを探すこと。
人は何かの項目をずらりと並べたとき、どの項目も同じ位重要だと思いがちだ。だが、多くの場合はそうではない。小さい項目に注目する前に「8割はどこにあるのだろう?」「なぜこの項目はこんなに大きいのだろう?」「という事は何が考えられるだろう?」と問いかけてみよう。
自分が肩入れしている考え方の弱みをいつも探したほうがいい。自分の意見に合わない新しい情報や専門以外の情報を進んで仕入れよう。自分に賛成してくれる人ばかりと話したり、自分の考えを裏付ける例を集めたりするより、意見が合わない人や反対してくれる人に会い、自分と違う考えを取り入れよう。
謙虚であると言う事は、本能を抑えて、事実を正しく見ることがどれほど難しいかに気づくことだ。自分の知識が限られていることを認めることだ。堂々と知りませんと言えることだ。 好奇心があると言う事は、新しい情報を積極的に探し受け入れると言うことだ。自分の考えに合わない事実を大切にし、その裏にある意味を理解しようと努めることだ。
2. 感想
世界を分断ではなく、全体で捉える視点を持て
- 本書が最も強く訴えているのは、「思い込みを乗り越え、データに基づいて世界をまっすぐ見ることの大切さ」です。
人間の脳は、極端な対立(たとえば「貧しい国」と「豊かな国」)や劇的な変化(たとえば「世界はどんどん悪くなっている」)を好むようにできています。しかし、実際には多くの人々が中間層に存在し、世界はデータを見る限り、過去よりも確実に改善されてきています。「分断」や「固定観念」がいかに現実の理解をゆがめるかを痛感させられる本であり、自分の視野を謙虚に疑いながら、事実に目を向けることの勇気を教えてくれます。また、自分が信じたい情報だけを集める確証バイアスに陥る危うさ、意見が違う人から学ぶ姿勢の大切さなど、今のビジネス社会にもそのまま通用する思考法がちりばめられています。
3. この言葉の活かし方
「分断思考」から抜け出す:対立構造に惑わされず、中間に目を向ける
「発展途上国 vs 先進国」「若者 vs 高齢者」「社員 vs 経営陣」など、つい物事を二項対立で捉えてしまいがちです。しかし、ほとんどの人や物事はその間に位置しており、白か黒かではなく、グラデーションがある。この視点を持つだけで、他者への理解も、課題の捉え方も大きく変わります。
実践例
• 研修や営業現場で使う資料を作る際、「二極化」ではなく「全体の分布図(例:4分類・マトリクス)」を使って説明する。
「8割はどこか?」を常に問う:重要度を見極め、思考の優先順位を鍛える
ToDoリストや会議の議題、プロジェクトの課題整理など、「すべてが同じくらい大事に見える」状態は、実は思考の混乱を生みます。
本書の教えにある通り、「なぜこの項目は大きいのか?」「本当に重要な8割はどこか?」と自問する習慣が、本質的な優先順位を見抜く力になります。
実践例
• 施策を立てるとき、「効果が大きい順」に並べる訓練をチームに導入(例:「インパクト×実現可能性マトリクス」)。
• 会議で話題が分散しそうになったら、「それは全体の中でどれくらいの割合なのか?」と問いを投げて、視点を整理。
「意見が違う人」に会う勇気:自分の見方に揺らぎを取り入れる
人間は、つい「自分の考えを支持してくれる情報」ばかり集めてしまいます。しかし、本書はそれを「思考の自動運転」と呼び、意識的に違う視点を取り入れる必要性を説いています。この揺らぎを取り入れる姿勢こそ、変化に強い個人や組織の根幹になります。
実践例
• SNSやニュースでも「自分が普段見ない意見」を週1回チェックする時間を作る(情報ダイエットの逆)。
「知らない」と言える強さ:謙虚な姿勢が、チームの心理的安全性を生む
「知っているフリ」をしないことは、弱さではなく強さ。とくにリーダーやマネージャーが「わからない」と言えることで、部下や周囲も安心して発言できる空気が生まれます。「知識」よりも「姿勢」の方が信頼を得る時代において、本書の謙虚さのすすめは極めて実践的です。
実践例
• 研修や会議の冒頭で「これは考える場であって、答えを出す場ではない」と宣言し、思考の柔軟性を促す。
4.まとめ
ファクトフルネスとは、「賢くなる」のではなく「見方を変える」習慣です。
• データに問いを立て、「重要な8割」にフォーカスする
• 異なる意見にこそ、自分を進化させるヒントがある
• 謙虚であることは、最も賢明なビジネス戦略である
世界を正しく見ることは、ビジネスを正しく進めることにつながります。
この思考法を、日々の選択や判断に組み込むことで、ノイズに振り回されない「芯のある思考」が身につくはずです。
5.「私の読書メモ」で紹介した本
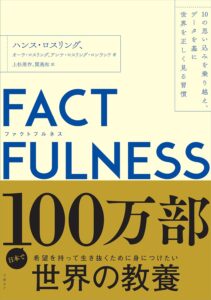
FACTFULNESS(ファクトフルネス) 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣(Amazon)
ファクトフルネスとは――データや事実にもとづき、世界を読み解く習慣。賢い人ほどとらわれる10の思い込みから解放されれば、癒され、世界を正しく見るスキルが身につく。世界を正しく見る、誰もが身につけておくべき習慣でありスキル、「ファクトフルネス」を解説しよう。(出版社より)
日曜の朝が楽しみになる。名著を通じてビジネスの知見を探究する読書会です。変化の激しい時代だからこそ、「賞味期限の短い、誰もが手にする本」ではなく、「時を超える本」を一緒に味わっていきましょう。毎月1回、日曜日に定期開催しています。
カテゴリー
・私の読書メモ