中小企業が社格を高める意外な盲点とは?
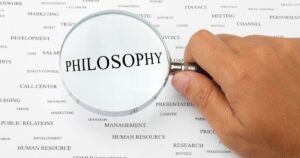
中小企業の経営者は、日々の業績向上や売上拡大に全力を注いでいます。
その真摯な努力の一方で、「社格」という目に見えない資産にまで意識を向ける余裕が持てないことも少なくありません。
稲盛和夫氏が説いた「フィロソフィ」には、企業が永続的に繁栄するための本質が語られています。
今回は、「社格を高めるとは何か」というテーマを通じて、経営の見えない力に光を当てます。
目次
1.「社格」とは何か──企業の人格という視点
2.稲盛フィロソフィに学ぶ、社格を形づくる4つの要素
3.企業が陥る「社格軽視」の盲点
4.明日からできる「社格を高める3つの実践」
5.まとめ:社格が企業の未来を決める
1.「社格」とは何か──企業の人格という視点
稲盛氏は「人に人格があるように、企業にも人格がある」と語っています。この企業の人格こそが「社格」であり、たとえ規模が小さくても、社会から「信頼できる会社」と見られるかどうかを左右する重要な要素です。社格は財務諸表には表れませんが、社員の言動、顧客との約束の守り方、地域社会への姿勢に如実に現れます。言い換えれば、社格とは「見えない信用力」なのです。
2.稲盛フィロソフィに学ぶ、社格を形づくる4つの要素
稲盛氏のフィロソフィは、「企業がどう生きるか」を定義する行動哲学です。その中核をなす4つの要素は、次の通りです。
1.会社の規範となるルール・約束事
社内での判断や行動の基準を明文化し、「何が正しいか」を共有します。
2.目的・目標を達成するための考え方
数字を追うだけでなく、目的達成のためにどのような姿勢・努力を重ねるかを問い直します。
3.すばらしい社格を与える考え方
「立派な会社だ」と社会から信頼・尊敬される存在を目指します。
4.人間としての正しい生き方を示す
最も根本的な要素です。社員一人ひとりの生き方が、最終的に企業文化を形づくります。
これらの4つは階層的な構造を持っています。
フィロソフィ4つの要素(稲森和夫 OFFICIAL SITE)
上の3つが「会社のあり方」を定め、4つめがその根幹を支える「人のあり方」を規定します。
企業を動かすのは制度でも仕組みでもなく、「人」です。だからこそ、経営者自身がまず「正しく生きる」姿勢を体現することが求められます。
3.企業が陥る「社格軽視」の盲点
企業の中には、「利益が出ていれば良い」「取引先との関係が保てていれば十分」と考える場合があります。しかし、社格を軽んじた経営は、短期的な成果を得ても長続きしません。なぜなら、信頼の基盤がないからです。
たとえば、社員が小さな約束を軽んじてしまうと、顧客との関係も徐々に脆くなります。一方で、たとえ小規模な企業でも、礼儀や誠実さを大切にしている会社には、取引先も地域社会も自然と信頼を寄せます。この「信頼の蓄積」こそが、長期的な成長を支える社格なのです。
企業の現場では、日々の売上や取引の安定を最優先にせざるを得ない状況も多くあります。その結果として、「利益が出ていれば十分」「取引先との関係が続いていれば問題ない」と考えてしまうこともあるかもしれません。しかし、社格を軽んじた経営は、短期的な成果を上げても長続きしにくいものです。なぜなら、組織の信頼という土台が育っていないからです。たとえば、社員が小さな約束を後回しにしてしまうと、顧客との関係にも少しずつ影響が及びます。反対に、たとえ小さな会社でも、礼儀や誠実さを大切にしている企業には、取引先も地域社会も自然と信頼を寄せます。この「信頼の積み重ね」こそが、長期的な成長を支える社格なのです。
4.明日からできる「社格を高める3つの実践」
社格は一朝一夕に築かれるものではありません。しかし、日々の小さな実践を積み重ねることで、確実に高めることができます。
今日から始められる3つの取り組みを紹介します。
1.言葉を整える
挨拶や報告、メールなど、日常の一言一言に誠意を込めましょう。言葉は社格の鏡です。
2.約束を守る
小さな納期や返答期限も軽視しないこと。信頼は「約束を守る習慣」から生まれます。
3.社会との関係を意識する
地域活動への参加や環境への配慮など、利益以外の価値を生み出す行動を一つでも増やしましょう。
5.まとめ:社格が企業の未来を決める
稲盛氏は「企業とは人間の集団であり、その心が正しければ必ず繁栄する」と説いています。社格を高めるということは、経営理念を掲げるだけでなく、日常の判断や行動を「人として正しいかどうか」で選び続けることです。社員一人ひとりがその精神を実践し続ける企業には、必ず社会からの信頼と、長期的な繁栄が訪れることでしょう。
それは立派なスローガンではなく、社員への一言や小さな約束の実行かもしれません。
稲盛フィロソフィに学ぶ、社格を形づくる4つの要素のなかで、「会社の規範となるルール・約束事」つまり、社内での判断や行動の基準を明文化し、「何が正しいか」を共有する。これこそが「理念」です。「理念を軸に行動する組織づくり」こそ、今の中小企業に最も求められています。
その実践法を体系的にまとめたのが、私の書籍『理念×行動=自律するチーム:理念を行動に変える自律するチームの実践体系』です。もし本コラムで「社格を高める経営」の本質に共感されたなら、ぜひこちらで一歩深く学んでみてください。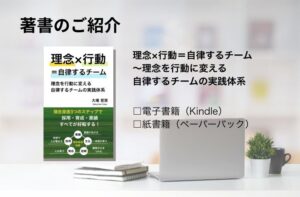 理念×行動=自律するチーム:理念を行動に変える自律するチームの実践体系 大場 宣英(著)
理念×行動=自律するチーム:理念を行動に変える自律するチームの実践体系 大場 宣英(著)
大場宣英の著書|育成マネジメントシリーズ
中小企業が社格を高める意外な盲点とは?
(C)大場コンサルティングオフィス










