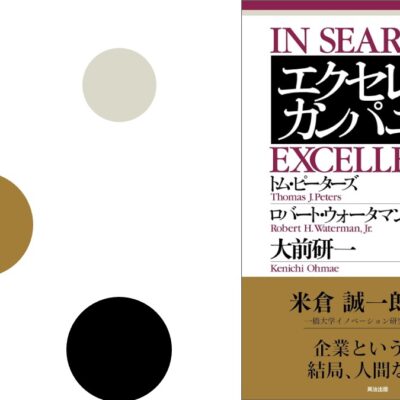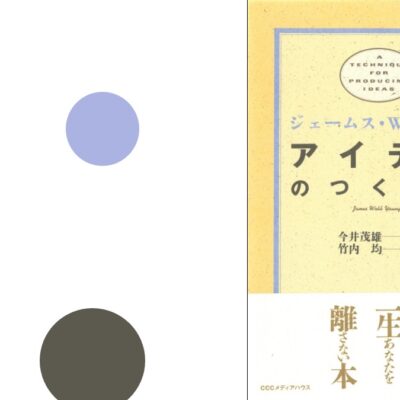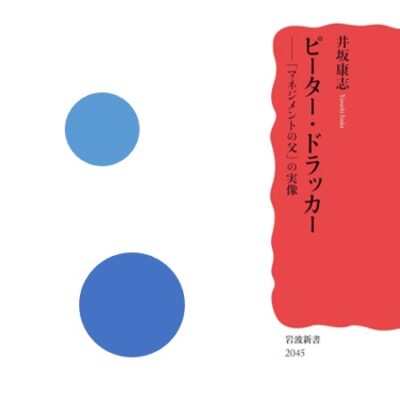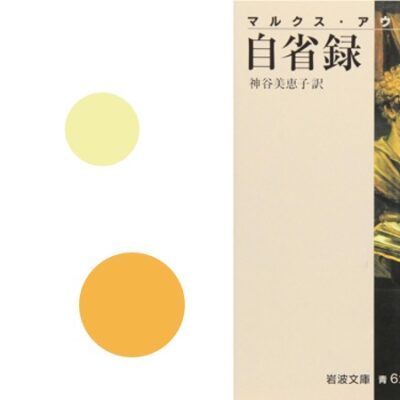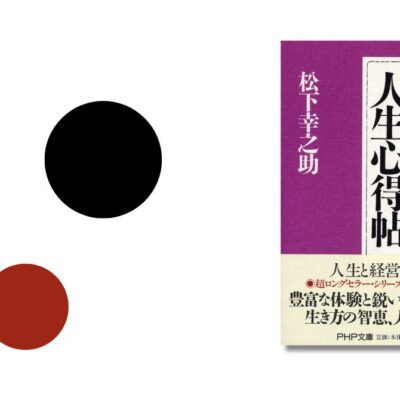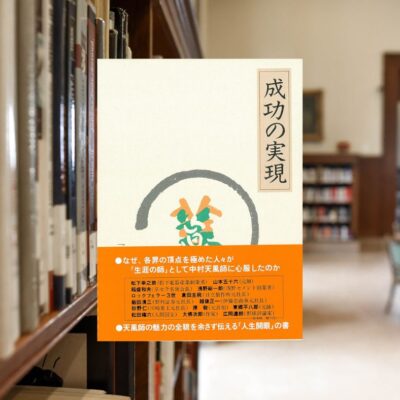プロフェッショナルの条件 いかに成果をあげ、成長するか 私の読書メモを紹介します。
著者:P・F・ドラッカー

目次
• 1.本書からピックアップ
• 2.感想
• 3.この言葉の活かし方
• 4.まとめ
• 5.私の読書メモで紹介した本
1.本書からピックアップ
数年ごとに、あらゆるプロセス、製品、手続き、方針について、「もしこれを行っていなかったとして、今わかっていることを全て知りつつ、なおかつ、これを始めるか」を問わなければならない。もし答えが、ノーであれば、「それでは今、何を行うべきか」を問わなければならない。そして行動しなければならない。
生産性の向上には継続学習が不可欠である。仕事を改善し訓練するという、テイラーが実践したことだけでは不十分である。学習に終わりは無い。まさしく日本企業の経験が我々に教えているように、訓練の最大の成果は、新しいことを学び取ることにあるのではなく、既にうまくいっていることをさらにうまく行えるようにすることである。
優先順位の決定については、いくつかの重要な原則がある。第一に、過去ではなく未来を選ぶことである。第二に、問題ではなく機会に焦点を当てることである。第三に、横並びではなく自らの方向性を持つことである。第四に、無難で容易なものではなく、変革をもたらすものに標準を合わせることである。
私が13歳の時、宗教の素晴らしい先生がいた。教室の中を歩きながら、「何によって憶えられたいかね」と聞いた。誰も答えられなかった。先生は笑いながらこういった。「今答えられるとは思わない。でも、50歳になっても答えられなければ人生を無駄にしたことになるよ」。今日でも私は、この何によって覚えられたいかを自らに問い続けている。これは、自らの成長を促す問いである。なぜならば、自らを異なる人物、そうなり得る人物として見るよう仕向けられるからである。
2. 感想
「今ならこれを始めるか?」と問い続ける勇気
- ドラッカーが提唱する「もしこれを今から始めるとしたら、やるか?」という問いは、現代のビジネスにおいて最も鋭いセルフチェックだと感じました。私たちは、既存のプロセスや制度に慣れや過去の実績にしがみつきがちです。
- しかし、本当に成果をあげ、変化に適応するためには、“過去の延長線”を断ち切る覚悟と、「いまここ」から問い直す勇気が必要です。この問いを習慣化できれば、事業も個人も、惰性に流されず、常に“意志ある選択”を続けることができる。そんなプロフェッショナルでありたいと思います。
継続学習とは「問題解決」ではなく「長所強化」である
- ドラッカーは、学びの真の価値は「問題を克服すること」ではなく、「すでにうまくいっていることをさらに高めること」だと喝破します。これは、一般的な「弱み克服」重視の発想を超える成長の本質です。現代において、突出した成果を出す人や組織は、欠点を平均化するのではなく、強みをさらに伸ばして、独自の価値を際立たせる道を選んでいます。
- 学びとは、自分の持ち味をさらに深める営みであり、「足りないもの探し」ではなく、「光るもの磨き」です。この視点の転換が、プロフェッショナルとしての飛躍を生むのだと思います。
「何によって憶えられたいか」という究極の自己定義
- ドラッカー自身が語る、13歳のときの問い。「何によって憶えられたいか」。この問いには、自分自身を“未来の存在”として見つめる力があります。なぜなら、「いまの自分」ではなく、「これからなりたい自分」「実現したい価値」に焦点を合わせる問いだからです。
- ビジネスの成果や肩書きではなく、「私は、どんな貢献によって憶えられたいか」。この問いを持ち続ける人だけが、自らを成長させ、時代や環境を超えて価値を残す存在になれるのだと思いました。
3. この言葉の活かし方
「今から始めるとしたら?」という視点で業務・プロジェクトを見直す
具体的な活かし方
• 既存のサービス・制度をすべて「今、顧客や市場に本当に必要か?」という観点で棚卸しする
実践例
プロジェクトレビューの際、成果だけでなく「プロジェクトの存在理由そのもの」を再確認するルーチンを作ることで、常に時流に即した事業運営ができるようになる。
継続学習は「強みを伸ばす」ことにフォーカスする
具体的な活かし方
• 社内評価や面談でも「あなたがすでに得意なことで、さらに磨きたいものは何か?」という問いを投げかける
実践例
若手社員の研修で「苦手克服プログラム」ではなく、「あなたの武器をさらに研ぎ澄ますプログラム」を用意し、自己効力感と専門性を高めるキャリア支援を行う。
「何によって憶えられたいか」を自己成長の軸にする
具体的な活かし方
• チームの1on1やコーチングで、「あなたはどんな価値を残したいか?」という未来志向の問いを活用する
実践例
社内表彰制度を「成果」だけでなく、「組織に与えたポジティブな影響」や「周囲への貢献」にも焦点を当て、社員一人ひとりが「憶えられたい存在」を意識する文化を育む。
4.まとめ
本書は、成果を出すための技術論ではなく、「いかに生き、いかに成長するか」という根本的な姿勢の指南書です。
• 問題解決ではなく、強みの伸長にフォーカスする学び
• 自らに「何によって憶えられたいか」を問う、未来志向の自己定義
この三つの姿勢を持ち続けることこそ、変化の激しい時代においても成果をあげ、成長し続ける真のプロフェッショナルへの道だと確信します。
あなたは、何によって憶えられたいですか?
そして、それを実現するために、今日どんな一歩を踏み出しますか?
5.「私の読書メモ」で紹介した本

プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか(Amazon)
日曜の朝が楽しみになる。名著を通じてビジネスの知見を探究する読書会です。変化の激しい時代だからこそ、「賞味期限の短い、誰もが手にする本」ではなく、「時を超える本」を一緒に味わっていきましょう。毎月1回、日曜日に定期開催しています。
カテゴリー
・私の読書メモ
Copyright Ooba Consulting Office All Right Reserved.
本コンテンツをを無断複製することや転載することを禁止します